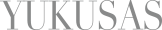1781年に祇園、切通しにて創業。初代いづみや卯兵衛の一字をとって「いづう」と名付けられた。
鯖寿司は、もともと京の町衆がハレの日や祭りの日に好んで食べていた家庭の味。それを料理人として初めて世に送り出したのが、いづうだ。専門店を構えるにあたり、素材、製法に吟味を重ねた初代。いづうの鯖姿寿司は、滋賀県産の江州米と、北海道産の真昆布、そして日本近海で獲れた脂ののった真鯖でつくられ、そのおいしさを保つため竹の皮で包まれる。鯖姿寿司は、巻かれた昆布から鯖とご飯へ旨みが移るため、時間の経過とともに風味が変わるのも味わい深い。
また、いづうの歴史と切っても切れないのが、お茶屋の存在だ。花街独自の文化に見合うよう、器や盛付けにも工夫がなされている。焼物なら古伊万里(こいまり)、漆器なら輪島と、お座敷の格に見合う最高級品の器を用い、盛付けには、芸妓さん、舞妓さんが取り分ける際に崩れないようにとの配慮から、”石段積み”と呼ばれる独自の方法を採用する。
1970年からは長く花街の旦那衆に愛されてきた味を、本店にて頂けるようになった。訪れた際は祇園の文化や歴史に想いを馳せながら、鯖姿寿司を味わいたい。また寿司は持ち帰りもでき、お土産としても好評だ。持ち帰りの包装紙には、日本一への気概をこめて富士山、三保の松原が描かれており、掛け紙には京都人が大切にする季節感を表現。春から冬まで6種類あり、一年通して鯖姿寿司に彩りを添える。
長い歴史の中で洗練され続けてきた鯖姿寿司は、もはや芸術品といえるだろう。